チューリングの夢
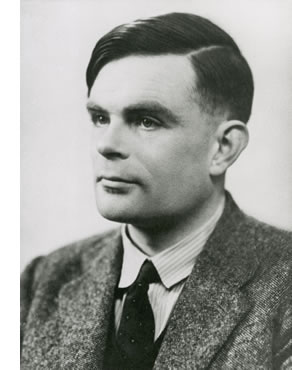 京都にも梅雨が来て、疎水沿いには鮮やかな紫の紫陽花が咲いている。ちょっと前までは、夜の疎水をたくさんの蛍が舞って、川面に映る蛍の光が、うっとりするほど美しかった。
勉強に行き詰まると、散歩にでかけるようにしている。
特にアテもなく、ぷらぷらと歩く。
僕が忙しく考え事をしなくても、自然は絶え間なくはたらいている。
川の水は流れ、鳥が鳴き、虫は飛び交い、風が吹く。僕の小さな考え事の外側で、自然は、僕の知らない大きな思考を思考している。そのことに、ほっとする。
風のおとづれに耳を澄ませながら、ぼうっと山の方を見上げていると、ブ~ンと蚊が飛んできて、チクリと刺す。京都の蚊は、東京の蚊より羽音がなんだか determined な感じで、ちょっとやそっとじゃ退散しないぞという、覚悟の決まった感じがある。刺されると痒いけれど、悠々とした山の姿を見上げていると、僕も蚊も同じひとつのものに所属しているという感じがしてきて、蚊も敵とは思えなくなってくる。
刺された首を掻きながら、西の方の山間に沈んでいく夕陽を眺める。
古来より人は、太陽が沈みゆく西の方に、生命の帰っていくべき場所を見出してきたという。同じひとつのものから生まれた生命が、また同じひとつの場所へと帰っていく。
生まれたばかりの幼子は、母乳を自分の内から来るものとして認知するという。母も子も同じひとつのもので、内と外の区別がない。ところが、あるときこどもは、「そと」ということに覚醒する。このとき、それまで同じひとつのものだった母が他者となり、環境となる。そうして同じひとつのものから「片方」 *1 を失った片割れとして、「私」が誕生する。「片方」を失うことで、私は私になる。これが「私」に運命づけられた孤独の起源である。
生きることは、失われた片方を探すことである。
生の側にとどまって、片方を失ったまま、同じ一つの「もう片方」と出会おうとすることである。
人は言葉を使って、同じひとつのものに、二つの名前をつけようとする。
「物質と生命」と言ったり「生と死」と言ったり「善と悪」と言ったりして、同じひとつのものに、違う二つの名前をつけたがる。そうしていつの間にか、違う二つの名前の指し示していたものが、同じひとつのものであったことを忘れてしまう。
いつしか失われた片方にも、私と違う名前が与えられ、私とは他なるものとして切り離される。切り離されたうえで、それを分析したり解析したり制御したりしようとする。そうして、自然について思考する。しかし、このときの自然は、もはや僕らと同じひとつの自然ではない。
失われた片方と、同じひとつのものとして出会うこと。
それはいかにして可能だろうか。
そもそも mathematics という言葉は、ハイデガーによれば、ギリシア語の ta mathemata という言葉から来ているという。古代ギリシアの人々は、世界の諸物を、 ta physica, ta puiumena, ta chremata, ta pragmata などと呼んで区別した。例えば ta physica とは「おのずからそうであるところのもの」という意味であり、 ta puiumena には「人の手によってつくられたところのもの」という意味がある。その中で、ta mathemata には「手元にあるものをあらためて掴みとるというかたちで獲得されるところのもの」という意味合いがあるという。「掴む」こと、しかも「すでに手元にあるものを掴みとること」が、mathematics という言葉の原義なのである。
つまり、未知なるものと、同じひとつのものとして出会うこと、それこそが本来の言葉の意味での mathematics という行為の本質なのである。
今年はアラン・チューリングの生誕百周年である。
チューリングは、上で言ったような意味で、字義通り、真の意味での mathematician であった。彼は、人間と機械、男性と女性、生命と非生命、という区別を前にして、常にその背後に同じ一つのものを見出そうとする精神の持ち主であった。チューリングにとっては恋人も、機械も、非生命も、みな彼と同じひとつの失われた片方であった。失われた片方と、同じひとつのものとして出会いたいという激しい情熱が、彼の生涯と研究を駆動した。
チューリングは実際、幾度も大切な片方を失った。
一歳のときに両親はインドに去り、チューリングは退役軍人の家に預けられた。幼くして両親からの温かい抱擁を失ったチューリングは、徐々に夢想的で非社交的な性格へ変わっていった *2 。
また、パブリックスクール時代には、チューリングはみずからが恋を寄せた親友のモルコムを病で失っている。これもまた、チューリングにとっては、かけがえなのない片方の喪失であった。
こうして、通常の生物学的次元、あるいは社会的次元で失われた片方を、より高次の宇宙的次元で取り戻そうとするかのように、チューリングの中には、壮大な数理的構想が育まれていった。
透明な孤独を深めていったチューリングの魂から、そのあまりに偉大な数理的構想が生み落とされたのは、彼がまだ24歳のときのことである。彼は一九三六年の歴史的な論文 *3 の中で、ヒルベルトの決定問題を解決するために、 LCM ( Logical Computing Machine )を構想した。このLCM が後に、チューリングの論文を読んだチャーチによって “Turing Machine ” と命名々されることになる、現代のコンピュータの原型である。
チューリングマシンは、紙と鉛筆と時間を資源に計算する人(computer )をモデルとした仮想的な機械である。ありとあらゆる機械的な手続き(=アルゴリズム)が、このチューリングマシンによって実行可能であると考えられている(Turing ’s Thesis)。特に、チューリングマシンにおいては、プログラムとデータが、ともにテープ上の数字列として実現されるため、同じ数字列があるときにはプログラムとして、あるときにはデータとして振舞う。この数字列の両義性を使って、チューリングは、あらゆるチューリングマシンの動作をシミュレートできる万能チューリングマシンを構成してみせた。
この万能チューリングマシンのアイディアがあまりにも強力であったために、のちに、人間の知能でさえも、このチューリングマシンによってシミュレートできるのではないかという考えが生まれ、人工知能研究に火がつくことになるのだが、チューリング自身は決してチューリングマシンを過信していたわけではない。
実際、チューリング自身が、誰よりも人間の知性とチューリングマシンとのギャップに自覚的であったようで、彼自身、より人間の知性に近い機械をつくろうと、様々な試行錯誤を繰り返している。
チューリングが人間の計算過程により近いと考えたのは、チューリングマシンよりも、むしろ一九三九年に出版されたチューリングの博士論文 *4 の中で導入された神託機械(Oracle machine ,O- machine )の方であったのではないかと思う。チューリングはこの論文の中で、神託(oracle)を参照しつつ非決定論的な飛躍をする神託機械の理論的な可能性に(神託は機械的には実現不可能であるというコメントとともに)触れている。
この論文の中でチューリングは、「数学的な推論は大雑把には直観( intuition)と創造性( ingenuity )の二つの能力の組み合わせによって実現されていると考えられる」 *5 とした上で、数学的推論から直観的側面を一掃することの不可能性を論じている。
こうした記述からも、チューリング自身、人間の知性にはチューリングマシンに回収不可能な側面があることを認めていたことが分かる。その上でなお、機械と人間の知性を同じひとつのものとして、なめらかに接続する夢を追い続けていたのである。
チューリングは41歳のとき、青酸中毒でこの世を去った。おそらくは自殺であると考えられているが、その詳細は謎に包まれている。チューリングは、私たちにたくさんの夢を託して、この世を去った。結局、いまだにチューリングマシンを超える計算の概念は確立されておらず、「計算」と「知性」のあいだには、決定的な溝が広がったままである。
チューリング誕生から百年を迎え、僕らはチューリングの恩恵に与りながら、いまやチューリングが生きたのとはまったく違った環境に取り囲まれている。それ自身決定論的なアルゴリズムに支配されていながら、人間の検索を「神託」として、問いに答えるというよりも、答えに相応しい問いを計算し、膨大なデータの「意味」を計算し続ける検索エンジンはまさにチューリングの神託機械のようであるし、ウェブそのものが、自然現象を神託とする巨大な O-machine を形成しつつある。ここでは、チューリングの意味での計算概念をいかにして超えていくかということが、いかにもリアルな問題になってくる。
チューリングの仕事を引き継ぎ、チューリングを超えていくのは僕らの仕事である。
チューリングマシンは、おそらく人類史上最も生産的な道具であろうコンピュータを生み、そのコンピュータはまた、人類史上最も破壊的な兵器の設計と制御に用いられるようになった。しかし、これ自体はチューリングの目指したことでも、チューリング自身の思想を直接に反映した結果でもない。
チューリングの計算概念を深めていった先で、僕らが僕らの失われた片方と、同じひとつのものとして出会う日がいつかやってくるとすれば、そのとき「コンピュータ」は、いまとはまた違った姿と役割を担うようになっているだろう。電子回路を素子とする閉じた機械の計算や、脳の内部の計算だけでなく、それらを包含し、それらを制約する、さらに大きなレベルで走る計算ということについて語る言葉を僕らが手にする日が遠くない未来にやってくるだろう。そのとき私たちは、コンピュータを、自然について分析し、制御するための道具として使うことを卒業し、僕らが自然とともに思考する大きなネットワークのうちに、新たなコンピュータを見出すようになっているかもしれない。
そのときはじめてコンピュータは、その本来の言葉の持つ意味:「com - putare(共に、考える)」ということを体現するようになるだろう。
チューリングが乗り越えられたとき、はじめてチューリングの夢は達成されるのである。
◆
本論稿は、チューリング生誕百周年を記念して PICSY blog に寄稿させていただいた記事「チューリングの夢」に加筆・修正を加えたものである。
京都にも梅雨が来て、疎水沿いには鮮やかな紫の紫陽花が咲いている。ちょっと前までは、夜の疎水をたくさんの蛍が舞って、川面に映る蛍の光が、うっとりするほど美しかった。
勉強に行き詰まると、散歩にでかけるようにしている。
特にアテもなく、ぷらぷらと歩く。
僕が忙しく考え事をしなくても、自然は絶え間なくはたらいている。
川の水は流れ、鳥が鳴き、虫は飛び交い、風が吹く。僕の小さな考え事の外側で、自然は、僕の知らない大きな思考を思考している。そのことに、ほっとする。
風のおとづれに耳を澄ませながら、ぼうっと山の方を見上げていると、ブ~ンと蚊が飛んできて、チクリと刺す。京都の蚊は、東京の蚊より羽音がなんだか determined な感じで、ちょっとやそっとじゃ退散しないぞという、覚悟の決まった感じがある。刺されると痒いけれど、悠々とした山の姿を見上げていると、僕も蚊も同じひとつのものに所属しているという感じがしてきて、蚊も敵とは思えなくなってくる。
刺された首を掻きながら、西の方の山間に沈んでいく夕陽を眺める。
古来より人は、太陽が沈みゆく西の方に、生命の帰っていくべき場所を見出してきたという。同じひとつのものから生まれた生命が、また同じひとつの場所へと帰っていく。
生まれたばかりの幼子は、母乳を自分の内から来るものとして認知するという。母も子も同じひとつのもので、内と外の区別がない。ところが、あるときこどもは、「そと」ということに覚醒する。このとき、それまで同じひとつのものだった母が他者となり、環境となる。そうして同じひとつのものから「片方」 *1 を失った片割れとして、「私」が誕生する。「片方」を失うことで、私は私になる。これが「私」に運命づけられた孤独の起源である。
生きることは、失われた片方を探すことである。
生の側にとどまって、片方を失ったまま、同じ一つの「もう片方」と出会おうとすることである。
人は言葉を使って、同じひとつのものに、二つの名前をつけようとする。
「物質と生命」と言ったり「生と死」と言ったり「善と悪」と言ったりして、同じひとつのものに、違う二つの名前をつけたがる。そうしていつの間にか、違う二つの名前の指し示していたものが、同じひとつのものであったことを忘れてしまう。
いつしか失われた片方にも、私と違う名前が与えられ、私とは他なるものとして切り離される。切り離されたうえで、それを分析したり解析したり制御したりしようとする。そうして、自然について思考する。しかし、このときの自然は、もはや僕らと同じひとつの自然ではない。
失われた片方と、同じひとつのものとして出会うこと。
それはいかにして可能だろうか。
そもそも mathematics という言葉は、ハイデガーによれば、ギリシア語の ta mathemata という言葉から来ているという。古代ギリシアの人々は、世界の諸物を、 ta physica, ta puiumena, ta chremata, ta pragmata などと呼んで区別した。例えば ta physica とは「おのずからそうであるところのもの」という意味であり、 ta puiumena には「人の手によってつくられたところのもの」という意味がある。その中で、ta mathemata には「手元にあるものをあらためて掴みとるというかたちで獲得されるところのもの」という意味合いがあるという。「掴む」こと、しかも「すでに手元にあるものを掴みとること」が、mathematics という言葉の原義なのである。
つまり、未知なるものと、同じひとつのものとして出会うこと、それこそが本来の言葉の意味での mathematics という行為の本質なのである。
今年はアラン・チューリングの生誕百周年である。
チューリングは、上で言ったような意味で、字義通り、真の意味での mathematician であった。彼は、人間と機械、男性と女性、生命と非生命、という区別を前にして、常にその背後に同じ一つのものを見出そうとする精神の持ち主であった。チューリングにとっては恋人も、機械も、非生命も、みな彼と同じひとつの失われた片方であった。失われた片方と、同じひとつのものとして出会いたいという激しい情熱が、彼の生涯と研究を駆動した。
チューリングは実際、幾度も大切な片方を失った。
一歳のときに両親はインドに去り、チューリングは退役軍人の家に預けられた。幼くして両親からの温かい抱擁を失ったチューリングは、徐々に夢想的で非社交的な性格へ変わっていった *2 。
また、パブリックスクール時代には、チューリングはみずからが恋を寄せた親友のモルコムを病で失っている。これもまた、チューリングにとっては、かけがえなのない片方の喪失であった。
こうして、通常の生物学的次元、あるいは社会的次元で失われた片方を、より高次の宇宙的次元で取り戻そうとするかのように、チューリングの中には、壮大な数理的構想が育まれていった。
透明な孤独を深めていったチューリングの魂から、そのあまりに偉大な数理的構想が生み落とされたのは、彼がまだ24歳のときのことである。彼は一九三六年の歴史的な論文 *3 の中で、ヒルベルトの決定問題を解決するために、 LCM ( Logical Computing Machine )を構想した。このLCM が後に、チューリングの論文を読んだチャーチによって “Turing Machine ” と命名々されることになる、現代のコンピュータの原型である。
チューリングマシンは、紙と鉛筆と時間を資源に計算する人(computer )をモデルとした仮想的な機械である。ありとあらゆる機械的な手続き(=アルゴリズム)が、このチューリングマシンによって実行可能であると考えられている(Turing ’s Thesis)。特に、チューリングマシンにおいては、プログラムとデータが、ともにテープ上の数字列として実現されるため、同じ数字列があるときにはプログラムとして、あるときにはデータとして振舞う。この数字列の両義性を使って、チューリングは、あらゆるチューリングマシンの動作をシミュレートできる万能チューリングマシンを構成してみせた。
この万能チューリングマシンのアイディアがあまりにも強力であったために、のちに、人間の知能でさえも、このチューリングマシンによってシミュレートできるのではないかという考えが生まれ、人工知能研究に火がつくことになるのだが、チューリング自身は決してチューリングマシンを過信していたわけではない。
実際、チューリング自身が、誰よりも人間の知性とチューリングマシンとのギャップに自覚的であったようで、彼自身、より人間の知性に近い機械をつくろうと、様々な試行錯誤を繰り返している。
チューリングが人間の計算過程により近いと考えたのは、チューリングマシンよりも、むしろ一九三九年に出版されたチューリングの博士論文 *4 の中で導入された神託機械(Oracle machine ,O- machine )の方であったのではないかと思う。チューリングはこの論文の中で、神託(oracle)を参照しつつ非決定論的な飛躍をする神託機械の理論的な可能性に(神託は機械的には実現不可能であるというコメントとともに)触れている。
この論文の中でチューリングは、「数学的な推論は大雑把には直観( intuition)と創造性( ingenuity )の二つの能力の組み合わせによって実現されていると考えられる」 *5 とした上で、数学的推論から直観的側面を一掃することの不可能性を論じている。
こうした記述からも、チューリング自身、人間の知性にはチューリングマシンに回収不可能な側面があることを認めていたことが分かる。その上でなお、機械と人間の知性を同じひとつのものとして、なめらかに接続する夢を追い続けていたのである。
チューリングは41歳のとき、青酸中毒でこの世を去った。おそらくは自殺であると考えられているが、その詳細は謎に包まれている。チューリングは、私たちにたくさんの夢を託して、この世を去った。結局、いまだにチューリングマシンを超える計算の概念は確立されておらず、「計算」と「知性」のあいだには、決定的な溝が広がったままである。
チューリング誕生から百年を迎え、僕らはチューリングの恩恵に与りながら、いまやチューリングが生きたのとはまったく違った環境に取り囲まれている。それ自身決定論的なアルゴリズムに支配されていながら、人間の検索を「神託」として、問いに答えるというよりも、答えに相応しい問いを計算し、膨大なデータの「意味」を計算し続ける検索エンジンはまさにチューリングの神託機械のようであるし、ウェブそのものが、自然現象を神託とする巨大な O-machine を形成しつつある。ここでは、チューリングの意味での計算概念をいかにして超えていくかということが、いかにもリアルな問題になってくる。
チューリングの仕事を引き継ぎ、チューリングを超えていくのは僕らの仕事である。
チューリングマシンは、おそらく人類史上最も生産的な道具であろうコンピュータを生み、そのコンピュータはまた、人類史上最も破壊的な兵器の設計と制御に用いられるようになった。しかし、これ自体はチューリングの目指したことでも、チューリング自身の思想を直接に反映した結果でもない。
チューリングの計算概念を深めていった先で、僕らが僕らの失われた片方と、同じひとつのものとして出会う日がいつかやってくるとすれば、そのとき「コンピュータ」は、いまとはまた違った姿と役割を担うようになっているだろう。電子回路を素子とする閉じた機械の計算や、脳の内部の計算だけでなく、それらを包含し、それらを制約する、さらに大きなレベルで走る計算ということについて語る言葉を僕らが手にする日が遠くない未来にやってくるだろう。そのとき私たちは、コンピュータを、自然について分析し、制御するための道具として使うことを卒業し、僕らが自然とともに思考する大きなネットワークのうちに、新たなコンピュータを見出すようになっているかもしれない。
そのときはじめてコンピュータは、その本来の言葉の持つ意味:「com - putare(共に、考える)」ということを体現するようになるだろう。
チューリングが乗り越えられたとき、はじめてチューリングの夢は達成されるのである。
◆
本論稿は、チューリング生誕百周年を記念して PICSY blog に寄稿させていただいた記事「チューリングの夢」に加筆・修正を加えたものである。